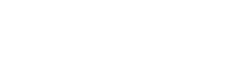GANET-TSUJI'S OWN MUSICAL INSTRUMENT
雅音人辻の所有楽器
主な楽器の紹介です。
手元には他にも様々な楽器がありますが、主として使っている楽器をご紹介します。ブログ記事とも連動していますので、そちらもご覧ください。
Ovation Super Adamas 1687-7
1980年製
1980年製のOvation Super Adamasです。詳細は、ブログに書いていますので、リンクをご参照ください。
Adamasは、カーボングラファイトと言われるグラスファイバーの一種で作られたギターで、カーマンコーポレーションという会社がもともとはヘリコプターの羽根に使われるために開発した素材でしたが、振動が多すぎて羽根には使えず、社長がカントリーのギタリストだったことから誕生したギター。
この当時のSuper Adamasは、実に素晴らしく、ギターというよりAdamasの音と言った方がピッタリきます。Ovationは、広く知られどんどん売れるようになってから、かなり品質が落ちてきてしまって、1983年以降と以前とは、まったく別モノというくらい作りも、音も、変わってしまっていますので、この時代のAdamasは、欲しいサウンドが出てくる貴重なギターで、今の時代のAdamasとは全く違います。大事に弾いて行こうと思います。
Ovationギター、昔は憧れの名器だった
Martin D-18
1973年製
1973年製のビンテージD18です。トップはスプルース、サイド、バックはマホガニー
この時代のD18は、どうなんだろう?とちょっと弾いてみてビックリしました。
何と軽やかな、軽いサウンド感、まるで歌いたくなるような、懐かしいように思う音なんですね。
サウンド感としてはフォークソングをまずは思い出してしまいますが、
レコーディングに威力を発揮してくれるギターなのではないかと思います。
誰よりも愛してる、あなたとラララなど、このギターでレコーディングを行っています。
Martin D18 1973年製ビンテージ
Martin D-35SQ
1989年製
私も、いつかはマーチンと思っていた一人です。D18,28,35,41と長い時間をかけて弾き比べて、自分にしっくりくるギターを自分で選びました。D35は音量も十分ありますが、音が太くて柔らかいですね。購入後どれだけ弾き込んだか、もちろん時間ではたとえようもないですが、もうすごい弾き方で、コンサートや、レコーディング、昔は、ストリートミュージシャンもやっていたこともあり、野外でも十分その威力を発揮してくれるサウンドで、このギターは、初めて、自分で納得することの出来たサウンドでした。このマーチンは、アコースティックのミュージシャンの私にとって、宝だと思っています。今では歳相応に音も変化してきまして、さらに骨のあるいいサウンドとなってきています。SQはトランスロッドのないタイプのものですが、ネックのソリは皆無ですね。非常に耐久性にもすぐれていますが、数多くのコンサート、録音で本当に酷使しまして、15年目にして、初めてオーバーホール。中の力木がはずれ、35特有の白いインレイがはずれてきてしまって大修理いたしました。今ではすっかり元気に、素晴らしい太いサウンドを聴かせてくれています。
一生のつきあいになる心の友ともいうべき、僕の音楽活動になくてはならない、大切な相棒です。
2020年現在のピックアップは、LR BaggsのM1のアクティブが搭載されています。やはり、初期は、このギターにサンライズ(マグネチック)を付けていましたので、やはり、相性はマグネチックが合うかと思います。このM1の前は、同じくLR BaggsのiBeamを搭載していましたが、これが相性が合わなかったのです。Gibsonには相性が抜群ですが、Martinには合わないという、このあたりもギターの面白いところです。
2011.2.26-27レコーディングレポート
BleedLove SC251R
1990年頃 (初期型)
何とも聞きなれないギターメーカー。 ブリードラブ。
YAMAHAが代理店でしたが、2024年にKORGが代理店になり、YAMAHA時代に一気に日本に入ってきました。
比較的新しいギターメーカーで、設立は1989年となります。
ブリードラブというのは、実は人の名前。アメリカのオレゴン州に生産拠点があります。
少し小ぶりなギターではありますが、最新のテクノロジーが満載のギターで、 「Breedloveでは、従来の製法に一手間を加え、制作途中のトップ・バック材のタップトーンをマイクで拾い、周波数を測定。測定した周波数を基準に最終的に職人の手によりハンドヴォイシングすることで個々のサウンドのばらつきを最小限に抑え、サウンドを最適化する工夫を製造工程に取り入れています。」とイシバシ楽器のサイトにもありますが、
生の音の周波数を測定して作られているんですね。実にばらつきの少ない、かっちりした感じ、いい感じと思えるサウンド感を持っています。
このギターは、トップを薄くしてなりやすい設計にしていますが、どうしても弦の張力でトップが膨らんでしまう、という難点を解決するために
ブリードラブブリッジトラスという木製のL字型の器具が内蔵されていまして、これで、鳴りを重視しながら、トップの膨らみも抑えるというアイデアも導入されています。
現在のブリードラブは後付けということになっているようですが、この初期型ははじめからブリッジトラスが内蔵されていました。
このギターにはピックアップが内蔵されていまして、LRBaggsのHifiというピックアップが後付けですが、導入されています。
このピックアップは、ブリッジの下に敷くタイプではなく、2つの素子をトップの裏に張り付けるタイプで、生音の影響がないのが特徴で、これだけ生音に周波数まで
測定されてつくられているものを、ブリッジの下に何かを入れるというのには相当抵抗がありましたので、
このタイプのピックアップにしました。
BleedLove SC251R
K.Yairi DY-41
1979年製
2020年3月に東京で手に入れた、K.YAIRIの1979年製 DY-41です。辻仕様になるまで徹底的に調整を重ねて、2020年11月現在で、 ベストコンディションになりました。DY-41ということは、K.YairiのMartinD-41のコピーモデルです。このギターは1979年製。この当時の音ですから、素材が大変豊富で良い時代の素材が使われているので、今では考えられないほどの鳴りの良さがあります。古き良き時代、といいますが、Gibsonなどは1950年代のギターなどは、素材があったわけで、どれを弾いてもすごい鳴りで鳴りますので、素材の良し悪しというのはどうしてもギターに影響しているのはよく分かります。1979年というと、日本では、第二次フォークブームの真っ最中。ギター一本で何が出来るかということを問われていた時代でもあり、この当時のギターは、アコースティックギターだけで何が出来るかという、1つの勝負に出ている気概を感じさせてくれる迫力ある音がします。ピックアップは、LR.Baggsのアンセムを付けております。バランスもサウンド感も弾き心地も最高の1本です。
1979年 K.YAIRI DY-41入手!
K.Yairi 辻スペシャル
1993年頃
サイドバック:シカモア(グレート・メイプル)、トップ:スプルース 欠かせない大事なギター辻スペシャルです。最近分かったのですが、このギターは、ヤイリギターの社長さんの60歳を記念して制作された、SY-4というギターを開発するときに作ったサンプルギターではないかということでした。ということは、1993年頃製ではないかと想像できますが、ヤイリのリペア松尾さんによると、それとは全く違うというお話でした。ということは形だけ似ているが中身は全く違うということでしょうか?分からないことが多いですが、すごいいい音で鳴りまくるギターです。他の代わりはなかなか見つかりません。
その中でピックアップ付きでとても珍しいです。オーストラリア製のピックアップらしく、もしかするとコールクラークのギターに搭載されているものではないか?という話もあります。このギターは、シカモアという素材で、別名、グレートメイプルと呼ばれている材料。2020年現在では、ものすごい鳴りのギターに成長しました。Yairiさんといえば、落ち着いた感じの大人のサウンド感といいますか、暴れない感じといいますか、そんなイメージなんですが、これ、ギャンギャンいいますから!!何か、弾いてるだけで、ストレス発散になるような、感じのサウンド!!レコーディングもラインで録りますが、とても他の楽器との相性が良いサウンド感でとても良い感じです。また、どんどん表に出そうと思っています。実に弾きやすい、サウンドもよくまとまったギターです。このあたり、さすが、世界のK.Yairiです。
ヤイリギター訪問、ギター、チャランゴ調整!!
YAMAHA FG500
1970年~71年製
1969年から72年にかけて生産されていたのですが、このFG500は7桁のシリアルで、この頃はいわゆるフォークブームで、ギターが爆発的に売れ出し
暫定的につけたシリアルということで年代が70年~71年というところまでしか特定できない状況です。
このFG500は、YAMAHAのFGシリーズの最高峰として君臨し、何と、バックがハカランダ単板(ブラジリアンローズウッド)という超豪華な仕様となっています。
ハカランダは、希少性だけではなく、音についても、独特なサウンド感があり、よく「バリーン」という音と表現する方もみえますが、そんなイメージになっていまして
音量もかなりあります。
今では、ワシントン条約により、輸入はかなり少ないという状況ではありますが、完全に入って来ないというわけではないようです。
FGシリーズは基本的にはオール合板ですが、このFG500については、トップ スプルース単板 バック ハカランダ単板 サイド ハカランダ合板 という仕様になっています。
当時の最高峰と言われるだけあるすごい仕様ですね。
古いギターは弾きこなされているので、これからが力の見せ所かもしれませんね。
YAMAHA FG500 ハカランダバック単板
Truth TN-35
2001年製
トップ:スプルース、サイド、バック:マホガニー
この楽器は、愛知県の弥富町というところにForMというギター工房を構える、福原さんという作家の作品です。当時マホガニーのギターは個性という感覚でみなさん語っておられるところをよく耳にしておりましたが、どうしてもマホは鳴らないというイメージしか、ありませんでした。しかし、このギターと出会い、今までのイメージをくつがえす、立ち上がりのいい、はっきりとした、さらに繊細なサウンド。音量が半端ではない大きさ。これにはびっくりしました。ギブソンのビンテージ等で採用されているダブルXブレイシング。要するに、トップの裏には、力木で大きな×が上下に2カ所というレイアウトで設置されています。これ、実はローズのギターでこれをやると、鳴らなくなるのですが、マホだと、これが鳴る様になるという、制作者本人もとても不思議とのことでした。大きなヘッドに「Truth」のロゴ。とっても印象的で、コンサート、レコーディングには欠かせないギターです。これこそ、ローズと個性が違う、僕の中ではマホのハイエンドギターといった印象の、大事なギターです。2011年、木製ピックガードを付けてもらいました。LR BaggsのIbeamActiveを搭載。生音を殺さないのが非常によいピックアップです。
愛知県のギター&ウクレレ工房「ForM」福原さん訪問!
Cole Clark FL1EC-BM
2019年製
サイドバック クイーンズランドメイプル トップ ブンヤ オール単板
オーストラリアのギターメーカー、コールクラークのギターです。
素材も聴いたことのない名前かと思いますが、オーストラリアの素材を使っています。オーストラリアのギター、メイトンを作っていた方が独立して立ち上げたギターメーカーです。
FL1~FL3までのグレードがあって、このギターは、FL1ですが、ピックアップが、FL2、FL3で使われている、コールクラーク自慢のナチュラルピックアップが搭載されています。
以前は、FL1だけ、2wayのピックアップでFL2、FL3とは区別されている状況でしたが、今では、装飾の違いという状況かと思います。
サウンド的には、生音は、バランスの良い、はっきりとしたサウンド感ですが、ピックアップを通したアンプから出る音は、非常にふくよかでビックリするくらいの生っぽいサウンド感があります。
歌モノ、また、ソロギターにもいいかと思う様なオールマイティーギターかと思います。2022年現在の代理店はイシバシ楽器ということで、一気に知名度も広がっている印象があります。
試奏も出来ますので、イシバシ楽器で試してみてくださいね。特にピックアップを通した音が凄いギターです。
ネックも少し広めの握りになっていますので、弾きにくいという方もいらっしゃるかもしれませんが、僕にはジャストフィットです。
このクオリティーは素晴らしいので、これからもっと世に出てくるのでは?と思います。
Cole Clark(コールクラーク)ギター 入手
Martin DC-X2E BRAZ 12-string
2024年頃
サイドバック ハイプレッシャーラミネート トップ スプルース単板
このMartinは、メキシコ製の廉価版Martinなんです。バックがよく聞きなれない素材?ということで、
ハイプレッシャーラミネートとは クロサワ楽器のサイトより
HPLとはオガクズなどを圧縮して板にしたもの。エコロジー&コスト削減で採用されている側面もありますが、 非常にタフな素材なのでギターの取り扱いにまだ不安が残る方でも安心してお使いいただけます。 こちらのモデルはアコギでは伝説的な木材であるブラジリアンローズウッド材パターンのHPLを使用。 見た目にもこだわりを持った方には受け入れやすいスタイルです。 エントリークラスの値段で発売されていますが、骨組みの組み方などで高効率化を図り、驚くほど豊かなサウンド。 その他ネック材にはセレクトハードウッド、指板とブリッジ材にもセレクトハードウッドを採用。 「ネックの形状」など「規格」的なものは高級モデルと同一で製作されている為に、クラスを超えた演奏性を誇ります。 実はエレアコ仕様なので、ある程度弾けるようになってライブや録音をしてみたくなってもそのまますぐにお使いいただけます。ラインサウンドもグッド。 付属:オリジナルギグバッグ、Martin正規保証書
ということで、バックの木目が何とハカランダなんですが、プリントなんですよ。(笑)
生音もなかなかいいサウンド感ですが、ピックアップを使ったときのサウンド感が素晴らしい。
12弦ギターというのは登場機会は少ないのですが、無いと困るというギターなので、貴重な存在です。
Martin DC-X2E BRAZ 12-string
Godin Multiac Nylon Duet
2003年製
プロの世界で、よく使われているエレガットです。Godinと書いて、ゴダンと呼びます。この2003年のMultiac NylonはDuetということで、ピエゾとコンデンサーマイクと両方とも対応していまして、この赤いツマミがコンデンサーのマイクのスイッチになっています。トレブル、ミドル、バスのレバーの他、コンデンサーとピエゾのミックス具合も決められるレバーも搭載。
出力はキャノンとホーンと両方とも使えて、キャノンはファンタム電源にも対応。
サウンドも、上手く聴きやすい部分をピックアップしている感じのサウンド感。さすがに世界中のプロアーティストが使用するだけありますね。大事に弾いて行きたいと思います。
GODIN(ゴダン)Multiac Nylon Duet 2003年入手!
K.Yairi CE-2 エレガット
2000年製
サイド、バック:ローズウッドトップ:スプルース
これは大珍品!当初はサンプル用のガットギターです。そこに、後付けで、ピックガードが付いて、現在カタログに掲載されている、CE-2です。
ピックアップ付き。現在、コンサートでたまに使用しています。このギターのネックは、何と、スチール弦用のネックが付いているんです。ですから、フォークネックタイプのガットギター。要するに、ネックが、クラシックギターの様な幅広タイプではなく、フォークギターの様にネックがほそくて握りやすい形になっています。静かなギターサウンドを丁寧に弾く様な感じの楽曲は、こういうギターで演奏したりするといいですね。ネックが細すぎるっていう一面も。しかし、ピックアップされたサウンド面は実によく出来ています。まとまりがあるというか。使いやすいサウンドですね。
雅音人Xmas 無事に終了。素晴らしいコンサートになりました!
Gamboa アルマジロチャランゴ
製造年不明
これを見ると、何??このグロテスクなもの??と言われそうですが、これぞ、本物のチャランゴ。南米のボリビア、ペルーの楽器で、今や、幻のチャランゴと言ってもいいのではないでしょうか?このバックは、なんだと思いますか??タイトルにありますので、分かると思いますが、アルマジロの甲羅なんです。毛もはえています。もともとアルマジロは食用とされていたので、この甲羅は捨てられていました。しかし、この甲羅を使って何か出来ないか?ということでチャランゴ制作が始まったと言われています。そして、本末転倒、食用の甲羅のみを使用していたのが、楽器用にアルマジロを捕るようになって、ついには生息数も減って、ワシントン条約で保護されるようになりました。ということで、今や、幻となっています。
チャランゴという楽器は、フォルクローレで高音を担当する楽器で、基本的なチューニングはウクレレと同じで副弦となっています。G-C-E-A-Eというチューニングで副弦となっていますので、10弦です。実は、日本人が一番好きな音と言われているので是非生サウンドを聴いてみてください。Gamboaというのは、ガンボアと読みまして、チャランゴ製作者の名前です。ボリビアのフアン.ガンボアの制作です。このアルマジロチャランゴは、ピンから切りまでありまして、中には虫の湧いているようなものも存在しています。特に土産物としてのチャランゴもあり、
その手のものは、楽器としてのクオリティーを保っていないものもありますので、要注意。このガンボアチャランゴは、かなりクオリティも高く、非常によい状態の個体です。
アルマジロチャランゴを入手しました。
K.Yairi 木製チャランゴ KK-46 No.49
製造年不明
現在の世界のK・Yairiのマスタークラフトマン、小池健司さんの作品です。この楽器はチャランゴっていいます。まるでパット見ウクレレみたいですけどね。実は、これ、フォルクローレで使う楽器なんです。弦は10本です。チューニングはギターでいう6弦側から(チャランゴでは5弦(10弦)から)G-C-E-A-Eの並びで復弦になっています。ちょっと楽器を知っている方は、G-C-E-A?これウクレレじゃん!そう言われるかもしれませんね。そうなんです。これ、ウクレレのチューニングに3弦と同じEのオクターブ違いが加わっただけ。押さえ方はウクレレとほぼ同じなんです。サウンドを聴いてみると、あ~この楽器の音だったの~??なんて、顔と名前が一致していない昔からの知り合い的なサウンドですよ。たまにはフォルクローレとかにも使いますが、このチャランゴとカズーでフォーク系の楽曲を演奏してしまったり、やりたい放題です。だけど、この猛烈な弾き傷。すごいでしょ?もう穴も開いてきてしまって、まるでウイリーネルソンのギターの様な風格まで出てきました。すごく強く弾いても応えてくれる個体なだけに、そう弾いてしまうのですが、そのおかげで、音はすごいボリュームで、いい楽器です。日本人が一番好きっていうサウンドだそうです。2010年8月18日、このチャランゴに小池さんのサイン入りのラベルが付きました。機種名は、KK-46 No.49ということになりました。
ヤイリギター訪問、ギター、チャランゴ調整!!
Ceniza BY T&K パイナップルウクレレ コンサートサイズ ロングネック ゴールドラベル
2005年までの製造
ハワイのオアフ島のワイアナエに工房を構えるトーマスとキャサリンの夫婦2人だけで製作しているウクレレ工房です。このサウンドは、ちょっと弾くだけで、ポーンと音が飛び出してくる、突き抜ける様な明るいハワイアンコア単板の素晴らしいサウンドです。これは、僕の一番のお気に入りのウクレレです。この金ラベルというのは、2006年中に黒ラベルに変更されているそうですので、それ以前の作品ということになりますね。ロングネックの良いところは、弦長が長いので、チューニングが合わせやすい、弾きやすいというメリットがあります。それに、このネック、ご覧になって分かるかと思いますが、実は、ネックまでハワイアンコアです。素材にこだわる意気込みを感じられますね。それに、ピックアップ搭載で、どうもフィッシュマンのマイクが内蔵されている様です。ラインから出してもとても空気感のあるサウンドが得られます。とにかく癒されるサウンドです。これが僕のメインのウクレレですね。残念ながら、2010年にキャサリンさんが亡くなられてからはウクレレ作りはされていないという情報もあります。非常に貴重なウクレレとなりました。
ウクレレ6本目?